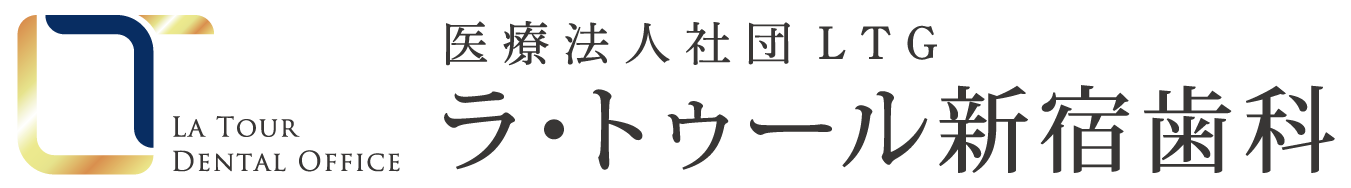24時間Web予約
歯列矯正の定義と目的
歯列矯正(しれつきょうせい、orthodontic treatment)とは、歯並びや咬合(こうごう)の異常を矯正し、機能的かつ審美的な改善を目的とする歯科治療の一分野です。不正咬合(malocclusion)は、審美的な問題だけでなく、咀嚼機能の低下、発音障害、顎関節症(TMD: Temporomandibular Disorders)、歯周病やう蝕(虫歯)のリスク増加といった健康上の問題を引き起こす可能性があります。
歯列矯正の主な目的は以下の通りです。
- 審美性の向上:歯並びを整え、顔貌の調和を改善。
- 咀嚼機能の向上:効率的な咬合を確立し、消化器官への負担を軽減。
- 発音の改善:歯列の乱れによる発音障害を矯正。
- 口腔衛生の向上:歯並びを整えることでブラッシングを容易にし、虫歯や歯周病を予防。
- 顎関節への負担軽減:正しい咬合を確立することで顎関節症のリスクを低減。

歯列矯正が必要な症例
歯列矯正が推奨される代表的な不正咬合の種類には以下のものがあります。
1. 叢生(そうせい、crowding)
歯が適切な位置に生えず、歯列が乱れている状態。ブラッシングが困難になり、虫歯や歯周病のリスクが高まる。
2. 上顎前突(じょうがくぜんとつ、maxillary protrusion)
上顎の前歯が過度に前方へ突出している状態。「出っ歯」とも呼ばれ、口が閉じにくくなる。
3. 下顎前突(かがくぜんとつ、mandibular protrusion)
下顎が上顎より前方に位置する「受け口」。咀嚼や発音に影響を及ぼすことがある。
4. 過蓋咬合(かがいこうごう、deep bite)
上顎前歯が下顎前歯を過度に覆い隠す状態。下顎前歯が上顎の歯肉を傷つける可能性がある。
5. 開咬(かいこう、open bite)
上下の歯が噛み合わず、前歯や臼歯に隙間が生じる状態。発音や咀嚼機能に影響を与える。
6. 交叉咬合(こうさこうごう、crossbite)
上下の歯が正常な位置関係を持たず、部分的に反対の位置で噛み合う状態。顎の成長に影響を与えることがある。
歯列矯正の種類
歯列矯正にはさまざまな方法があり、患者の症例やライフスタイルに応じた治療法が選択されます。

1. マウスピース矯正(アライナー矯正)
透明なマウスピースを用いて歯を移動させる矯正方法。代表的なものに「インビザライン」「クリアコレクト」などがあります。
特徴
- 目立たない
- 取り外し可能
- 痛みが少ない
- 清掃しやすい
2. ワイヤー矯正(ブラケット矯正)
歯にブラケットを装着し、ワイヤーの力で歯を移動させる矯正方法です。
種類
- メタルブラケット矯正:一般的なワイヤー矯正で費用が比較的安価。
- セラミックブラケット矯正:歯の色に近く目立ちにくい。
- 舌側矯正(リンガル矯正):歯の裏側に装置を装着するため目立たないが、発音や舌への違和感が大きい。
3. 部分矯正(MTM:Minor Tooth Movement)
部分的な歯列の乱れを矯正する方法。前歯だけの矯正などが可能。
4. 外科矯正
骨格的な問題が大きい場合に、矯正治療と外科手術を併用する方法。
歯が動く仕組み
歯列矯正では、歯に適切な力をかけることで骨のリモデリングを誘導し、歯の位置を変える。
- 圧迫側:骨が吸収される。
- 牽引側:新しい骨が形成される。
- 持続的な力の適用:矯正装置により適切な力をかけ、時間をかけて歯が動く。
歯列矯正のメリットとリスク
メリット
- 審美性の向上
- 口腔機能の改善
- 歯の健康維持
- 顎関節の健康改善
リスク
- 治療期間の長期化:数年単位の治療が必要。
- 痛みや違和感:装置の調整後に痛みを感じることがある。
- 歯根吸収の可能性:過度な矯正力により歯根が短縮することがある。
- 後戻りのリスク:保定装置(リテーナー)を適切に使用しないと歯が元の位置に戻る可能性がある。
歯列矯正の流れ
- 初診相談:口腔内の状態を診断し、矯正治療の必要性を評価。
- 精密検査:レントゲン、CT、口腔内スキャン(iTero など)を用いて詳細な診断を行う。
- 治療計画の立案:患者に適した矯正方法と治療期間を決定。
- 矯正装置の装着:選択した装置を装着し、歯の移動を開始。
- 定期的な調整:月に1回程度の調整を行い、歯の動きを管理。
- 保定(リテーナー):矯正終了後、後戻りを防ぐためにリテーナーを装着。
まとめ
歯列矯正は、審美的な改善だけでなく、咀嚼機能や発音、顎関節の健康維持にも重要な役割を果たします。症例に応じた適切な治療法を選択し、専門医の指導のもとで治療を進めることが重要です。